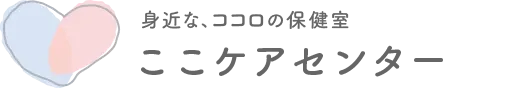職場での雑談や打ち合わせがとにかく緊張する。
何か話すたびに「変に思われていないか」と不安になる。
上司や同僚の表情が気になって、常に気を張ってしまう。
このような状態が続くと、疲労感だけでなく、「職場に行きたくない」と感じることが増えてくるかもしれません。
こうした背景には、「社交不安」と呼ばれる状態と、それに伴ううつ症状が関係している場合があります。
ここでは、社交不安とうつがどのように結びつくのかについて、心理学的な視点から考えていきます。
社交不安とは何か
社交不安は、人から否定的に評価されることへの強い恐れが中心にある状態です。
人前で話す、会話に加わる、注目される場面などで極度の緊張や不安を感じ、そうした状況を避けようとする傾向が見られます。
そのため、職場では特に苦手な場面が多く、朝礼や会議、同僚とのちょっとしたやりとりですら大きな負担になります。
本人としては普通にふるまおうとしていても、心の中では不安や自己否定の思考が渦巻いていることも少なくありません。
社交不安とうつの関連
社交不安のある人が長期的に人間関係のストレスを抱えていると、「どうせうまくいかない」「自分はこの場にふさわしくない」といった否定的な思考が強まりやすくなります。
このような考えが積み重なることで、うつ症状が出現することがあります。
実際の研究でも、社交不安症の方はうつ病を併発しやすいことが報告されています。ある調査では、社交不安症の患者の半数近くが、人生のどこかでうつ病の診断を受けた経験があるとされています。
うつ状態になると、意欲やエネルギーが低下し、もともとの不安に立ち向かう力も弱まります。
その結果、社交場面への回避がさらに強まり、孤立感が深まるという悪循環に陥ることもあります。
職場での困りごとが悪化要因に
職場は、ある程度のコミュニケーションが求められる場です。報連相、会議での発言、飲み会など、さまざまな場面で「人と関わること」が求められます。
こうした環境に長く身を置くことで、社交不安のある人は慢性的なストレスを受けやすく、それが気分の落ち込みに拍車をかけることがあります。
また、周囲に「気にしすぎだよ」「もっと自信持てば」と言われることで、かえって自己否定の感情が強くなることもあります。
これは社交不安とうつの併存において、見逃されやすいポイントの一つです。
自分を責めすぎないためにできること
まず大切なのは、「うまく人と関われない自分はおかしい」という捉え方を手放すことです。
社交不安やうつ症状は、意志や努力の問題ではなく、脳の働きや認知の傾向に影響されて起こるものです。
また、少しずつ緊張する場面に慣れていく取り組み(エクスポージャー)や、思考の偏りに気づき修正する訓練(認知再構成法)など、症状に対して有効とされる方法も複数あります。
「緊張しながらも関われた」という経験を丁寧に積み重ねていくことが、気分の安定につながる一歩になります。
必要なときは専門家に相談してください
社交不安と職場でのうつ症状が重なっていると感じる場合には、早めに専門家に相談することをおすすめします。
社交不安症もうつ病も、心理療法や薬物療法などにより改善が期待できる病気です。
どちらか一方ではなく、両方に目を向けたサポートを受けることで、より安定した回復が見込めます。
人との関わりに不安を感じることは、誰にでもあることです。
けれど、その不安が日々の生活や気分にまで影響を与えているときには、ひとりで抱えず、支援を受けることが回復への第一歩になります。
焦らず、少しずつ自分に合ったペースで進んでいきましょう。