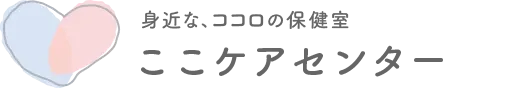会議に参加することは、多くの人にとって緊張を伴う場面です。特に社交不安のある人にとっては、その場が大きな心理的負担となることがあります。周囲の目が気になったり、発言を求められることへの恐怖が強まったりするためです。ここでは、社交不安の人が会議中にどのようなことを感じやすいのかを、心理学的な視点から整理してみましょう。
他人から受ける評価への過敏さ
社交不安の特徴のひとつは、他者からどう見られているかを過剰に意識することです。会議中であれば、自分の発言の内容や声の調子、表情などが常に評価されているように感じやすくなります。「的外れなことを言ったらどうしよう」「つまらない人間だと思われるのではないか」といった考えが頭を占め、発言のハードルが高くなってしまいます。実際には周囲がそこまで厳しく見ていない場合でも、本人にとってはとても大きな恐怖となります。
発言に伴う強い緊張
会議では、発言の機会を避けられないことがあります。社交不安のある人は、自分が話す番が近づいてくると心拍数が上がり、汗をかいたり、声が震えたりといった身体的反応が出やすくなります。このような身体反応自体がさらに「緊張しているのがバレるのでは」と不安を強める悪循環を生みます。心理学的には、こうした過覚醒状態が注意を奪い、内容を伝えることに集中できなくなると考えられています。
頭の中の反すう
会議中に「自分の発言は変ではなかったか」「今の表情は不自然だったのでは」といった思考が頭の中で繰り返されることもあります。これを認知行動療法の用語で「反すう」と呼びます。反すうが強いと、現在進行中の会議の内容に集中できなくなり、ますます不安や自信のなさが強化されてしまいます。このため、会議が終わったあとも長時間にわたり、自分の発言や態度を振り返っては苦しむことが少なくありません。
回避行動としての沈黙
社交不安の人は、発言すること自体を避けようとする場合もあります。意見を求められないように視線をそらす、発言を短くして早く終わらせる、あるいは体調不良を理由に会議を欠席することもあります。こうした回避行動は一時的には不安を和らげますが、長期的には「自分は話せない人間だ」という思い込みを強め、社交不安を維持してしまうことが知られています。
認知行動的な理解
認知行動療法の枠組みでは、社交不安における会議中の困難は「否定的な自動思考」と「回避行動」の組み合わせで説明されます。「うまく話せなかったら評価が下がる」という思考が不安を高め、発言を避ける行動につながります。その結果、「やはり自分はダメだ」という信念が強まり、不安が慢性的に続くのです。実際の研究でも、社交不安を抱える人は自分に対して厳しい評価をしやすいことが報告されています。
対処のヒント
会議中の社交不安に対処するには、いくつかの工夫があります。ひとつは、自分の思考に気づき、事実と解釈を区別することです。「周囲が笑った=自分を馬鹿にした」というように短絡的に結びつけず、別の可能性を考えることが有効です。また、小さな発言から練習することも役立ちます。たとえば、会議冒頭の挨拶や簡単な報告だけを意識的にこなしてみることで、不安の強さを少しずつ和らげることができます。さらに、深呼吸や筋弛緩法といったリラクセーションを使うことで、身体反応を落ち着けるのも効果的です。
まとめ
社交不安のある人は、会議中に他人の評価を気にしすぎたり、発言のたびに強い緊張を感じたりしやすい傾向があります。否定的な思考と回避行動の組み合わせによって不安が長引くことも多く、これが日常生活や仕事に影響を及ぼします。大切なのは、不安を「異常なもの」と捉えるのではなく、認知や行動のパターンとして理解し、少しずつ修正していくことです。
必要な時は専門家に相談してください。社交不安が強く、会議や仕事に大きな支障をきたしている場合には、心理療法や薬物療法など、専門的な支援が有効です。焦らず、自分に合った方法を見つけながら、不安との付き合い方を整えていくことが回復への第一歩となります。