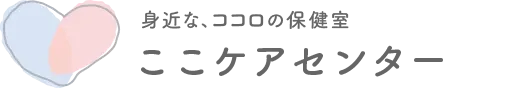- 職場の人間関係に強いストレスを感じている。
- 会議で何を言えばいいか分からず黙ってしまう。
- 雑談に入れず、孤立しているように感じる。
そのような状況が続くと、次第に心が疲れ、職場に向かう気力が失われていくことがあります。
こうした背景には、「対人スキルの不足」や「対人不安」と、うつ病の関係が潜んでいる場合があります。
ここでは、職場における対人スキルとうつとの関連について、心理学的な観点から整理してみましょう。
うつと対人場面の困難はなぜ起こるのか
うつの症状には、意欲の低下、思考の鈍り、自己評価の低下などがあります。
そのため、職場で人とやりとりする際に「自分の意見なんて言う価値がない」「何を話してもうまくいかない」といった否定的な思考が頭を占めやすくなります。
また、以前なら自然にできていたやりとりがぎこちなくなり、自信を失ってしまうこともあります。
会話がうまく続かない、相手の反応を読み取れない、言葉を選ぶのに時間がかかる――そうした一つひとつの経験が、「人とうまくやれない」という感覚を強めてしまうのです。
もともとの対人スキルと発症のリスク
もともと人とのやりとりに不安を感じやすい人、失敗を極端に恐れる人は、職場の対人ストレスを抱えやすい傾向があります。
心理学の研究でも、社会的スキルが低いと感じている人ほど、対人関係からくる慢性的なストレスを受けやすく、うつを引き起こすリスクが高まることが示されています。
もちろん、すべての人が流ちょうに話せるわけではありません。
それにもかかわらず、「話せない自分はダメだ」「場の空気を読めないのは恥ずかしい」といった強い自責の感情があると、うつを助長してしまうことにつながります。
対人スキルの問題は努力不足ではない
職場でのやりとりに困難を感じていると、「自分が努力していないせいだ」と思い詰めてしまうこともあるかもしれません。
しかし、対人スキルは単なる技術ではなく、安心感や自己評価、認知のスタイルなど、さまざまな要因に支えられています。
うつ状態にあるときは、これらの要素が大きく揺らぎやすくなります。
話しかけようと思っても身体が動かない、気を使いすぎて何も言えない、そうした状態は「甘え」ではなく、病気に伴う変化として自然に起こりうることです。
少しずつ対人場面に慣れていくために
うつ症状があるときは、まず「完璧に話そう」とするのをやめることが大切です。
自分の話し方を否定せず、「まずは挨拶だけ」「一言返事をするだけ」といった、小さなステップから始めてみることで、少しずつ安心できる場面が増えていきます。
また、対人スキルは練習やフィードバックによって少しずつ育てることができるものです。
カウンセリングや社会技能訓練(SST)などの支援を受けながら、自分に合ったやりとりのスタイルを見つけていくこともひとつの方法です。
必要なときは専門家に相談してください
職場の対人関係がつらく、日常に支障が出ている場合は、一人で抱え込まずに専門家に相談することをおすすめします。
うつの影響で対人スキルが発揮しづらくなっているケースもあれば、対人不安がもともと強く、それが長期的に気持ちを圧倒していることもあります。
医師や公認心理師といった専門職は、どちらの可能性も含めて適切な見立てと支援を提供してくれます。
どんなコミュニケーションも、最初はうまくいかないことがあります。
けれど、必要以上に自分を責めることなく、できることから一歩ずつ取り組んでいくことで、対人場面に対する負担感は少しずつ和らいでいきます。
焦らず、自分に合ったやり方を探していきましょう。