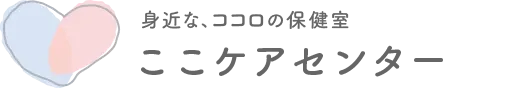気分が落ち込む日や不安が強まるときは誰にでもあります。けれど、それが一時的なものなのか、それとも「うつ病」や「不安症」といった状態に発展しているのかを見極めるのは簡単ではありません。自分では「疲れているだけ」と思っていても、実際には治療やサポートが必要な場合もあるのです。ここでは、不安やうつに早めに気づくための視点を整理してみます。
気分や感情の変化に注目する
まず大切なのは「気分の変化がどれくらい続いているか」を意識することです。落ち込みや不安感が数日で自然に回復することはよくあります。しかし、一定の期間を超えて続いている場合には、うつ病や不安症のサインである可能性が高まります。
うつでは「気分の落ち込み」「喜びや興味を感じられない」といった変化が目立ちます。不安症では「理由がはっきりしないのに落ち着かない」「心配が頭から離れない」といった状態が続きやすくなります。
身体に出るサインを見逃さない
不安やうつは心の問題と思われがちですが、身体にもしばしば表れます。食欲が落ちる、眠れない、疲れがとれないといった症状が長引く場合は注意が必要です。不安が強いときには動悸や息苦しさ、胃の不調などが出ることもあります。
これらの身体症状が検査で特別な異常がないのに続くときには、心の状態が影響している可能性を考える必要があります。
思考や行動の変化を見る
不安やうつが強くなると、思考や行動にも変化が出てきます。たとえば、「どうせ自分にはできない」といった否定的な考えが増える。人と会うのを避ける。普段なら簡単にできる作業に取りかかれない。こうした変化は、気分の変動とあわせて重要なサインとなります。
特に、物事を悲観的にしか見られなくなっているときや、先のことを考えるのがつらいときには、専門的な支援が必要な段階に入っていることもあります。
早めに気づくための工夫
自分では気づきにくいときもあるため、日記をつける、気分の記録アプリを使うなど「状態を見える化する」ことが役立ちます。客観的に振り返ることで、「思ったよりも落ち込みが続いている」と気づけることがあります。
また、周囲の人から「最近元気がない」と指摘されるのも重要なサインです。他者の目からの気づきは、自分では見逃している変化を教えてくれることがあります。
まとめ
不安やうつに気づくためには、気分の変化がどれくらい続いているか、身体や行動にどのような影響が出ているかに注目することが大切です。単なる疲れだと思って放置すると、状態が悪化してしまうこともあります。
必要な時は専門家に相談してくださいね。 しばらくの間落ち込みや強い不安が続いている場合には、早めに医療機関に相談することをおすすめします。小さな変化に気づき、無理をせず対応することが、回復への第一歩となります。