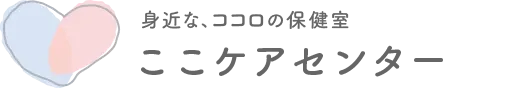10th Anniversary
10周年記念対談
ここケアセンター
10年を振り返って〜認知行動療法とリワーク支援のこれから〜

設立の経緯や想いをあらためてお聞かせ下さい
理事長:
設立の経緯は大きく3つ、あります。
まずは、復職支援を気軽に利用していただくということ。
10年前、復職支援はまだメジャーではなくて。気軽に受けられるものではなかったです。
愛知県では、愛知障害者職業センターなど公的機関と一部の病院で受けられるくらい。
それも、県内で数カ所。休職者全体をカバーできているとはとても言えない状態でした。
私は大学院でうつ病のメカニズムに関する研究をしてきて。うつ病に罹患してから復職するまでの大変さは分かっていました。
復職に至るまでにはさまざまなステップがあります。それを1人で乗り越えるのはとてもむずかしいです。
専門家と一緒だったら乗り越えられることも、ある。さらに、行政と協力して何かしらの制度を使えたら気軽に利用してもらえるはず。
そんな考えがありました。

次に、心理師やカウンセラーをもっと身近に感じて欲しかったこと。
アメリカやイギリスでは心理師によるカウンセリングはすごくポピュラーなものです。
夫婦が定期的にカップルカウンセリングを受けるくらい。
日本では、どうか。
カウンセラーからカウンセリングを受けたと聞くと驚かれることも。
ぜんぜん気軽じゃないです。
精神科医に受診となると、さらに気軽ではなくなりますよね。
ということは、精神科医に行く手前の人たちは我慢しているわけです。
うつ病はちょっとした心の風邪。なんて聞きながらも、本格的にこじらせて心の肺炎になってからじゃないと精神科医に行けない。
その手前でもっと気軽に受けられる、保健室みたいなカウンセリング。
それも、専門家である心理師からのカウンセリングを受けられるような施設を作りたい。これが2つ目。
3つ目は、認知行動療法を学んだ心理師さんが活躍できる場を作りたかったこと。
私は、認知行動療法という心理療法を専門とした心理師です。
心理師の中には、認知行動療法を専門的に勉強した人は全体の2割もいないかもしれません。
しかし、認知行動療法は多くの研究によってさまざまな精神疾患に有効であると明らかになっています。
医師が薬を処方するように。心理師が科学的に根拠のある心理療法を提供する。これができていなのが、実情。
せっかく専門的に勉強しても活躍の場がない。そんな若い心理師さんたちが活躍できる場を作りたい。そんな想いもあって、施設を立ち上げました。
10年の中で強く印象に残っているエピソードは?
理事長:
私にとって、立ち上げ自体が印象深いというか苦労しましたね。とても。そもそもの話。復職支援で福祉制度を使うことが認められていなかったのですよ。前例がないという理由でね。休職者は会社に在籍しているのだから、会社が負担するべし。それが役所の考え。
でも、自治体によっては使えたのですよ。つまり、制度としては前例がある。というのが私の考え。この折り合いをつけることが大変でした。まずは名古屋市。そして各市町村の役所に対して。私たち心理師が電話で説得しましたね。
福祉制度をどうしても使いたかったのは、休職者が気軽に利用できる施設にしたかったから。カウンセリングは、1時間8,000円〜12,000円ぐらいかかります。地域差はありますがね。それが1割の負担で使えたら気軽ですよね。
今では、福祉制度は休職者も利用できると厚生労働省が発布しています。おかげで以前のような苦労はなくなりました。業界的にも、こんな苦労をしているのは当所くらいではないでしょうか。あきらめずに開拓できたことは、とても印象深いですね。
所長:
私は施設ができて2年ほどしてから入職しました。心理師としては長くいるメンバーになります。私も理事長と一緒に役所に電話をして説得した1人。
当時の苦労は懐かしいですね。中でも、いま当所があるCBT名古屋ビルを購入したことが印象深いです。
はじめは、伏見(名古屋市中区)にあるマンションの1室を借りて支援をしていたのですよ。福祉制度が使えて気軽に利用できる。ちゃんとしたカウンセラーが相談に乗ってくれる。と、評判になり休職者がひっきりなしに相談に来られました。
その結果、休職者であふれかえることもしばしば。マンション内で部屋を増やすにも限度がある。ということで、計画にあった自社ビルを前倒して購入することになるわけです。
5年後のことでしたね。銀行さんから多額の融資を受けたからには、後には引けない。やるしかない!という雰囲気は刺激的でした

理事長:
経営者としては怖かったよ。金額が大きかったからね。でも、銀行さんから私たちがやっていることを認めてもらえたのは自信になったよね。
おかげでスタッフも増えて。グループ全体で言えば4倍。今まで以上に手厚いサポートができるようになったと思います。
あと、長儀所長の言葉にあった「やるしかない!」は嬉しかったですね。覚悟をもって苦しいときを乗り越えてくれた。だから大きく成長できた。
彼はもともと心理師でしたが今は所長も兼任して。スタッフの育成はもちろん、施設の運営にも貢献してくれています。
私は、認知行動療法を専門にした心理師がどのように成長するか。それも見たかった。だから長儀所長の成長は本当に嬉しくて。
彼のような人材が増えれば、認知行動療法をもっと広めていくこともできると確信しています。これも私にとって印象深いことですね。
今現在における問題点、解決しないといけないポイント、現状の課題とは?
理事長:
この10年で、復職支援はかなり認知されるようになりました。
復職支援を含めたリワーク(復職・再就職)支援という言葉も出てきて、当所のような施設も増えました。
一見すると、いいことのように思えるかもしれません。ですが、私は今の状況をとても懸念しています。
私たちは、ある意味ビジネスモデルを作りました。
福祉制度を利用した休職者の支援。これ、真似ができてしまうのですよ。簡単に。大学で勉強をした心理師でなくても、なんちゃらカウンセラーでやれてしまう。
この状況をとても懸念しています。

私たち心理師は、疾患に合わせて科学的に根拠のある治療をします。
カウンセリングといっても、ただ話を聞くだけではないのです。休職者さんの多くは、うつ病や適応障害といった精神疾患に苦しんでおられる。
つまり、命の選択の重要な分岐点になることもあるのです。
にもかかわらず、ビジネスモデルだけを参考に勢いでやってしまう。
しっかりした知識もないまま参入しようとする。そんな事業者さんが垣間見える今の状況に危機感を覚えます。
所長:
私も同感です。
ただ、私たちがどれだけ勉強しているか。認知行動療法に取り組んでいるか。支援者に対して指導を徹底しているか。といった、当所の良さがうまく伝わっていないことは課題かもしれません。
休職者さんからすれば、全国展開しているとか広告宣伝がうまいところに足を運びたくなる気持ちも理解できますからね。
支援の質では負けませんが、休職者さんがちょっとずつ分散しているのは実感としてありますね。
理事長:
確かに、昔ほどの爆発的な勢いはないよね。
でも、この10年で当所の他にも施設が増えたから分散するのは仕方がないこと。
福祉制度だから適切なサービスが提供できているのであれば、当所が1人勝ちしようとは思わない。
ただね。それには前提があって。ちゃんとした心理師やカウンセラーによる適切な支援が受けられる施設であれば、ということ。
そんな施設が増えれば、お互い切磋琢磨してサービスの質を高められる。業界全体の質も上がって、休職者さんにとってもプラスになる。

今はその逆。心理師の資格がなくても心理指導ができてしまう。専門的な勉強をしてきた私たちからすると、それって支援なの?と、疑問に思えてしまう。でも、制度的にやれてしまう。そこがとても歯がゆいです。
せめて、心理師やカウンセラーに対してどのような教育をしているかはオープンにして欲しいです。でないと、休職者さんの重要な選択を阻害することにもなりかねないからね。
ちなみに当所は、専門的な勉強をしてきた心理師がカウンセリングするのはもちろんのこと。
大学と提携して、第一線の先生から定期的に手ほどきを受けています。特に、1〜2年目の心理師はしっかり学び、組織としての質を保つようにもしています。
人材の育成で力を入れていること、心がけていることは?
所長:
当所では、スタッフ1人ひとりの自主性を大切にしています。上からあれこれしなさいと言うよりも、自分で考えて行動する。
そのほうが、自発的に学ぶしパフォーマンスも上がると思っています。
心理師で言えば、こんな疾患をお持ちの休職者さんがいますと。私はその分野が得意だから、担当させてください。といった具合に。
その分野を強みにしていきたいからやらせてください。そんな前向きな意見も積極的に取り入れて、チャレンジしてもらうようにしています。
その甲斐もあって、1人ひとりのパフォーマンスは確実に向上していて。組織としてうまく機能しているように思います。
理事長:
私もうまく機能しているように思います。自分たちで考えて学び、得意を伸ばしていく。
そんな心理師が活躍できる施設を作りたかったので、長儀所長の言葉はすごく嬉しいです。
ちょっと話がそれますが。心理師って国家資格なのですよ。
弁護士や医師と同様に。6年間、大学で勉強した学問がバックグランドにある。専門性がある。弁護士で言えば、交通事故が専門とか刑事事件が専門とか。医師であれば、外科や内科などありますよね。

私たち心理師はと言うと、どんな疾患にも対応しないといけないのが実情。例えば、200床ぐらいある病院に4〜5人の心理師がいたとすると全てを分担してフォローしないといけない。自分の得意・不得意に関係なく。
それは、成長を促す場になっていることは間違いないです。ただ、心理師を目指すきっかけにもなった関心がある疾患を得意にすることはむずかしい。するとどうなるか。せっかく心理師になったにも関わらず、自分の得意を活かせない・伸ばせないということになります。
そんな心理師さんが多くいることも知っていたので、活躍できる施設を作りたかった。
当所には30名以上の心理師がいます。1人ひとり、得意は違います。
でも、さまざまな疾患のエキスパートが揃っています。それは、得意を伸ばして活かせているから。だと思います。
所長:
確かにそうですね。心理師がやりたいことを選べるって場所によってはむずかしいですからね。当所はそれができるのは、心理師としてもやりがいに繋がりますね。あと、人材の育成で大切にしていることとして朝会がありますよね。
毎朝、1人ひとりが担当するクライエントさんについて発表して情報共有する場。状況を把握できるのはもちろんですが、周りからこんなアプローチがあるよ。とか、エビデンスあるよ。とか、意見がもらえるのは気づきにもなって成長を後押しできているのかなと。

理事長:
カウンセラーとして話を聞いていると、情報に没頭してしまうことがあって。偏った情報になりがちで、一歩引いてみることがとても大切。それを気づかせてくれるのが朝会だね。
特に、経験が浅いカウンセラーにとっては先輩からアドバイスをもらう場になっている。私も積極的に意見を言うよね。ときには厳しく聞こえることもあると思う。でも、それは休職者さんにとってベストな支援をしたいから。
スタッフに気をつかってサービスの質が落ちるのは本末転倒。でも、それを分かってくれている人ばかりが集まっているから。しっかり学んで、食らいついて、成長していると思います。
お2人がカウンセリングの現場で心がけていることは?
理事長:
長儀所長にも共通していることかもしれないけど、クライエントさんからどう見られるかというところですね。
私は今でも現場に立ちます。心理師として。カウンセラーとして。
ただ、あいち保健管理センター(現:ここケアセンター)の経営者でもあるのですよ。
会社で言えば、社長ですよね。
クライエントさんの中には会社や組織に不適応を起こして、うつなど疾患を抱えている人がいます。
そんな人からすると、私が職場の上司と重なって見えてしまうことがあります。

なるべく経営者の雰囲気は出さないよう、カウンセラーに徹するよう心がけています。
でも、言われちゃうのですよね。先生は経営者っぽい雰囲気ありますねって。そのあたり、私はうまくなくて。その点、長儀所長はうまいですよ。
所長:
ありがとうございます。そうですね、私も管理者の雰囲気はださないよう気をつけていますね。ただ、クライエントさんから話を聞いていると上司の気持ちも分かるのですよ。私にも感情はあるので。複雑な気持ちになることはあります。
でも、私の立場はあくまでクライエントさんに寄り添うこと。なので、自分の気持ちは脇に置いてカウンセラーに徹します。業界の中にはそれができず、クライエントさんともめる。そんなケースを耳にすることもありますが、私は一度もないですね。

あと、どの選択がクライエントさんにとって幸せか。ということを強く意識しています。例えば、人前で発表することが苦手な人がいるとします。仕事上、しなくてはいけない。でも、できない。それがきっかけで、会社に行けなくなったと。
この場合、発表しなくてもいい仕事に転職するやり方となんとかして乗り越えるやり方が考えられます。状況によって答えは変わると思います。カウンセラーによっても同様に。
私はクライエントさんの今後の幸せも考えて、なんとかして乗り終える方法を一緒に見つけたいです。逃げてもいいよと背中を押してほしい人からすると嫌かもしれませんがね。もし、どうしてもダメだったら別のやり方を探すか担当を変えるなどしてもいいと思います。
理事長:
担当を変えられるのは、当所のメリットだね。多くのカウンセラーの中から相性が合う人を見つけられる。
他の施設だったら、そうはいかないと思うよ。まずこれだけ心理師がいるところはないし、担当がついたら簡単には変えられないからね。
当所はわりと柔軟に変えることができるので、より相性の合うカウンセラーと治療に向き合うことができます。それをすることで、患者さんにとってもプラスになることが多いね。
これからの10年、どうしていきたいか?
所長:
私は、心理師のスペシャリスト集団を作りたいですね。選りすぐりの心理師が集まって、支援にあたる。適当な支援ではなくて、地域からも医師の先生たちからも頼られる。あそこにいけば安心だから、と言われる存在。
それも、愛知県にとどまらず全国に広げていきたいです。すでに出店計画はあるので、より多くの人たちのサポートができる日も近いでしょう。ただ、出店してダメだったから撤退。ではいけないので、地域の皆さまに信頼される施設を目指します。
理事長:
長儀所長が言ってくれた通りで。私が目指しているのは、あくまでもカウンセリングを受ける敷居を下げるっていうこと。なので、愛知県で終わっては意味がないわけです。東京や大阪に出店して支援の輪を広げていきたいです。
まずは東京。当所の顧問でもある原井宏明先生が東京にお住まいなので、提携しながら拠点を立ち上げます。近隣のクライエントさんに気軽に通っていただきたいですね。
それと、関東で認知行動療法を学んだ学生さんもそこに就職して活躍して欲しいです。育成にも力を入れていきたいので、愛知に負けないくらいの支援ができる施設を目指します。
お休みの日は何をしていますか?
理事長:
あまり息抜きはしないのですよ。うまくできなくて。長儀所長は、サウナでリフレッシュするなどうまくやっているようですけどね。私は家で動画を見たりダラダラしたり、ですかね。でも、そうしながらも仕事のことを考えていることが多いですね。
あとは、お酒ですかね。心理師で経営者をやっている仲間と飲みに行くことがあって。その時間はリフレッシュになっているかもですね。ただ、そこでも仕事の話ばかりしていますね。だから、完全にオフはないかもしれないですね。
最後に、理事長は経営者×心理師という立場でプライドや大切にしていることなどあれば教えてください
理事長:
どっちの手も抜かないことですね。経営者としては、当たり前ですが事業を拡大していく。心理師としては、第一線で支援にあたりクライエントさんから信頼されてスタッフから尊敬される存在でいる。
心理師かじりの経営者。経営かじりの心理師。これじゃあカッコ悪いですからね。クライエントさんにも申し訳ないし、スタッフにも示しがつかないと思っています。両立させる大変さはありますが、おかげで自分自身も成長できていると実感しています。