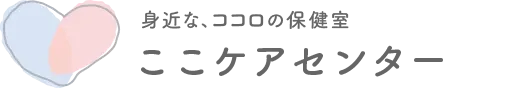急に胸がドキドキして、息が苦しくなる。めまいがして、立っていられなくなり、「このまま死ぬのではないか」とさえ思ってしまう。
そんな突然の発作に襲われた経験がある方は、パニック症という名前を聞いたことがあるかもしれません。
パニック症は、明確な原因がない状況で激しい不安発作を繰り返す状態を指します。何の前触れもなく突然始まるように感じられますが、心理学の視点からは、ある種の学習や思考のクセが大きく関係しているとされています。ここでは、認知行動療法の立場から、パニック症がどのように起こるのかを整理してみましょう。
「からだの変化」と「意味づけ」の悪循環
認知行動療法では、パニック発作は身体感覚の知覚とその意味づけから始まると考えられています。
たとえば、エレベーターの中で少し息苦しさを感じたとします。このとき、「あ、ちょっと暑いな」で終われば大きな問題にはなりません。しかし、「息ができない、やばい、パニックが来るかもしれない」と解釈した場合、その「不安」という感情がさらに交感神経を刺激し、実際に心拍数や呼吸数が上がっていきます。
その結果、最初の身体の変化が「本当に危険なもの」として再解釈され、さらに強い恐怖が生まれ、典型的なパニック発作に至ります。
このように、身体感覚とそれに対する「危険だ」という意味づけが、互いを強め合う悪循環が、パニック発作の本質にあるとされています。
「また起こるかもしれない」という予期不安
一度パニック発作を経験すると、多くの人は「またあの発作が起きたらどうしよう」と考えるようになります。これを予期不安と呼びます。
この不安は、実際の発作が起きていなくても、日常生活を大きく制限するようになります。
たとえば、電車に乗れなくなったり、買い物に行けなくなったりするのは、「その場所でまた発作が起こったらどうしよう」という思考が強く影響しているからです。
実際には、そうした場所自体が危険なのではなく、「そこで発作が起こったら困る」という思い込みが行動を制限しているというのが、認知行動的な理解です。
どうやって回復を目指していくか
認知行動療法では、パニック症に対して「回避せずに向き合う」練習を丁寧に進めていきます。たとえば、少しずつ不安のある場面に身を置いてみることで、「実際には何も起こらなかった」という経験を積み重ねていきます。
また、「ドキドキした=危険」という自動的な思考に対して、「これは不安のサインにすぎない」「少しすれば落ち着くことが多い」というように、柔らかい解釈に置き換えていくスキルも身につけていきます。
これらのアプローチを通して、身体感覚や不安との付き合い方を見直し、発作への恐怖を少しずつ和らげていくことが可能になります。
必要なときは専門家に相談してください
もし、不安によって生活が制限されていたり、外出が怖くなっているような状況が続いている場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。
パニック症は、「気の持ちよう」ではなく、明確なメカニズムがあるものです。正しく理解し、適切に対応することで、回復の道は開かれていきます。