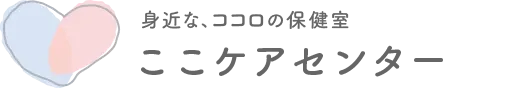連休や長期の休みが終わるとき、気持ちがどんよりして、仕事や学校に戻るのが億劫になる。頭ではわかっていても、体が動かない。そんな経験をしたことがある方も少なくないと思います。
このような「休み明けの不安」や「気分の重さ」は、多くの人に起こる自然な反応です。けれども、ときにはうつ状態に近いような、強い無気力や緊張感として現れることもあります。
いったい、なぜ長期休みのあとに、私たちはこんなにも不安を感じやすくなるのでしょうか。
切り替えの負荷が心にかかる
人は、日々の環境に慣れるようにできています。休みの間に身についた生活リズムや思考パターンは、それなりに快適に感じられるようになります。
ところが、休みが終わったとたんに再び早起きをし、複雑な人間関係や業務の中に戻らなければならない。心身にとっては、大きな切り替えのストレスがかかります。
この変化が急激であるほど、神経系は「脅威」とみなし、不安や焦燥感を引き起こします。いわば、エンジンの温まっていない車をいきなり全速力で走らせるようなものです。
先のことを考えると不安になる脳の仕組み
また、休み明けには「これから何をやらなければいけないか」「また同じような忙しい日々が始まる」といった未来への予測が浮かんできます。
このとき、脳の中では「扁桃体」という不安に関わる領域が活性化しやすくなるとされています。
特に、完璧主義的な傾向がある人や、職場での対人関係に負担を感じている人は、「ちゃんとこなせるか」「またうまくやれるだろうか」といった心配が強くなりがちです。その結果、気持ちが落ち着かず、体にも緊張やだるさが現れることになります。
うつ症状との重なりに注意する
このような休み明けの不安が一時的であれば、徐々に慣れていくことが多いですが、中にはうつ症状の入り口となるケースもあります。
特に、気分の落ち込みが長引いていたり、食欲や睡眠に明らかな変化があったりする場合には注意が必要です。
「仕事に戻るのが嫌」というだけでなく、「何もかも無意味に感じる」「自分はダメだと思えて仕方ない」といった考え方の変化があるときには、早めの対応が大切になります。
必要なときは専門家に相談してください
もし、休み明けの不安が何日も続いていたり、日常生活に支障をきたすほどになっている場合には、無理にがんばろうとせず、専門家に相談してみてください。
休み明けの不安は、「弱さ」ではなく「適応にかかる負荷」です。その背景には、脳と心の働きが関わっています。
不安そのものをなくすことはできなくても、「なぜ起こるのか」「どう付き合うか」を知るだけで、少しだけ見え方が変わってくるかもしれません。
自分に合ったペースを大切にしながら、少しずつ調子を取り戻していきましょう。