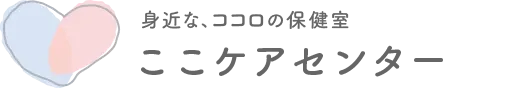仕事に打ち込んできたはずなのに、あるときから力が出なくなってしまう。今までならやれていたはずのことが、手につかなくなっている。まるで糸が切れてしまったかのように、意欲が湧かない。そんな感覚に心当たりのある方は、燃え尽き症候群という言葉を目にしたことがあるかもしれません。
燃え尽き症候群(Burnout)は、特に人を相手にする仕事をしている人に多く見られる反応で、長期間のストレスや過労、感情労働によって心身が疲弊し、無気力や自己評価の低下、仕事への嫌悪感などが現れる状態を指します。
1970年代にフロイデンバーガーという精神科医が初めて提唱し、現在では職業性ストレスの一種として国際的にも注目されています。
では、この燃え尽き症候群は「うつ病」とはどう違うのでしょうか。あるいは、まったく同じものなのでしょうか。
うつ病との違いと重なり
うつ病は、興味や喜びの喪失、気分の落ち込み、睡眠や食欲の変化、思考の遅さ、自己否定、希死念慮などを中心とする精神疾患で、医学的診断基準に基づいて診断されます。
いっぽう燃え尽き症候群は、特定の診断基準を持たない概念であり、医学的には疾患ではなく「職業性のストレス反応」として位置づけられることが多くあります。
しかし、実際には両者ははっきりと線引きできるものではありません。燃え尽き症候群の症状が持続した場合、うつ病の診断基準を満たすようになることもありますし、うつ病と診断された方の中には、発症の経緯として「仕事での消耗」が強く関与していた例も少なくありません。
つまり、燃え尽き症候群はうつ病の「前段階」や「きっかけ」となることもあり、状況によっては治療の対象にもなります。
メカニズムに着目すると見えてくること
燃え尽き症候群は、ストレスに長期間さらされた状態が続いた結果として現れることが多いとされます。とくに、努力しても報われない感覚、自分の感情を抑えながら仕事を続ける状況、役割の不明確さ、過剰な責任などが重なると、脳の報酬系の働きが低下し、意欲や達成感が得られにくくなっていきます。
こうした状態は、脳内の神経伝達物質のバランスにも影響を与えるため、うつ病と似たような症状が現れてくるのです。だからこそ、「単なる疲れ」や「やる気の問題」と見過ごさずに、精神的な不調として適切に向き合うことが求められます。
どう対処すればよいか
燃え尽き症候群に対しては、まず現在の働き方や生活スタイルを見直すことが第一歩となります。ストレス要因から距離を置き、休息を確保することが重要です。
過度な責任感や完璧主義、自己犠牲的な姿勢が背景にある場合は、それらの認知や行動パターンについても整理していく必要があります。
また、気分の落ち込みや意欲の低下が続く場合には、うつ病の可能性も考慮しながら、専門家に相談することが推奨されます。カウンセリングや認知行動療法、必要に応じた薬物療法など、状況に応じた対応が検討されます。
必要なときは専門家に相談してください
もし、「もう頑張れない」と感じる日が続いていたり、出勤のことを考えるだけで気持ちが沈んでしまうようであれば、それは燃え尽きのサインかもしれません。
早い段階で立ち止まり、信頼できる人や専門家に話を聞いてもらうことが、状況を変える第一歩になります。
疲れきった心を責める必要はありません。限界まで頑張ったからこそ、休むべきときが来ている場合も少なくはないでしょう。日々のなかで小さな変化を積み重ねながら、自分の心の声に耳を傾けていきましょう。