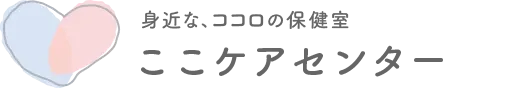仕事でミスが続いたり、人間関係のちょっとした出来事が気になって頭から離れなくなったりすることは、多くの人が経験することです。こうしたとき、私たちは「気分が落ち込んでいるから集中できない」とか「焦っているからうまく考えられない」と感じるかもしれません。実はこの感覚は的を射ていて、認知機能と感情のあいだには密接な関係があることが知られています。
認知機能とは何か
認知機能とは、情報を理解し、記憶し、判断し、行動に移すための基本的な能力の総称です。注意、記憶、思考、判断、実行機能(計画立てや切り替え、抑制など)といった複数の要素が含まれます。これらの機能は、日常生活や仕事、対人関係などあらゆる場面で土台となる働きをしています。
感情と認知機能の双方向の関係
感情と認知機能は一方向ではなく、双方向に影響し合う関係にあります。強い不安や怒り、落ち込みといった感情状態にあるとき、注意力や判断力、記憶力が一時的に低下することがあります。たとえば不安が強いと、頭の中が「失敗したらどうしよう」という考えで占められ、目の前の作業に集中できなくなることがあります。うつ状態では、思考や情報処理のスピードが遅くなったり、注意の範囲が狭くなったりすることが報告されています。
一方で、認知機能の変化が感情に影響を与えることもあります。たとえば注意がネガティブな情報に偏ると、悲観的な考えが強まり、不安や落ち込みを感じやすくなります。記憶でも、過去の失敗や嫌な出来事ばかりが思い出されると、感情面にも影響が及びます。このように、認知機能と感情は互いに影響し合いながら、私たちの心の状態を形づくっています。
うつ病における認知機能と感情の関係
うつ病では、気分や意欲の低下とともに、注意力、記憶力、思考の柔軟性といった認知機能の低下がよく見られます。たとえば、会話の内容が頭に入ってこない、仕事の手順がうまく覚えられない、判断が鈍るといった形で現れます。
この認知機能の低下があると、仕事や人間関係でミスや行き違いが起こりやすくなり、それがさらに自己否定的な感情や不安を強めるという悪循環に陥ることがあります。「また間違えた」「自分はダメだ」といった考えが強まることで、気分の落ち込みが深まることもあります。
向き合い方と実際的な工夫
感情と認知機能の関係を理解すると、「なぜこうなるのか」が少し見えやすくなります。まず重要なのは、落ち込んでいるときや不安が強いときに、一時的に集中力や判断力が低下するのは自然な現象であると理解することです。努力不足ではなく、心の状態が認知機能に影響を及ぼしているという前提に立つことで、自分を過剰に責めることを防げます。
また、認知機能の負担を減らす環境の工夫も有効です。作業手順を細かく書き出す、重要なことはメモを取る、一度に多くのことをこなそうとせず、作業を分割するなどの方法があります。気分が落ちているときには、大きな課題に一気に取り組むよりも、小さな単位で進める方が現実的です。
まとめ
認知機能と感情は切り離されたものではなく、相互に影響し合いながら私たちの心の状態をつくっています。不安や落ち込みがあるときに注意力や記憶力が低下するのは珍しいことではありませんし、逆に認知機能の偏りや低下が感情を不安定にすることもあります。
こうした関係を理解したうえで、環境や作業方法を工夫することで、悪循環を和らげることができます。
必要な時は専門家に相談してください。 認知機能の低下や感情の変化が生活や仕事に大きな影響を与えている場合は、一人で抱え込まずに医療機関や専門家に相談することが大切です。適切な支援によって、両者のバランスを整える手がかりが得られることがあります。