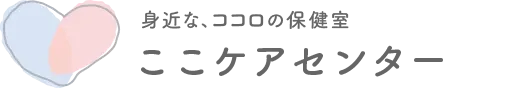なんだか落ち着かない。特に何があったわけでもないのに、体がそわそわする。
日常生活の中で、こうした「理由のない不安」に戸惑ったことはありませんか?
- ふとした瞬間に胸がざわつく
- 人と会うのが怖くなる理由が自分でもわからない
- 緊張しているのに、何に対してなのか説明がつかない
- 寝ようとすると不安が襲ってくる
- 「おかしくなってしまったのかも」と思ってしまう
このような「理由の見えない不安」は、現実に起こる現象なのですが、その背景には心理や身体の反応の仕組みが関係しているといわれています。
不安には「身体」から始まるものがある
不安という感情は、必ずしも「何かを心配している」という形で始まるわけではありません。
ときには、身体の緊張や自律神経の変化から先に生じ、それをあとから「理由づけ」しようとすることもあります。
たとえば、カフェインや睡眠不足、ホルモンバランスの変化、体調不良などでも交感神経が優位になり、身体が「戦うか逃げるか」の準備をしてしまうことがあります。
このとき、「今は安全なのに、なぜ体がこんなに緊張しているのだろう?」というギャップが、不安というかたちで認識されることがあります。
つまり、不安は「理由のある思考の結果」だけでなく、「身体の反応に引っ張られて生まれる感情」でもあるということです。
「考えすぎ」が不安を増幅させる
理由がはっきりしない不安ほど、人は理由を探そうとしてしまいます。「もしかして」「きっと」「また同じことが起こるかも」といった思考が繰り返されると、かえって不安は強まります。
これは、心理学では「心配」と呼ばれる状態です。不安の理由を何とか見つけようとする過程で、脳が危険信号を出し続けてしまうのです。
特に全般不安症のような状態では、このような理由のない不安や心配が慢性的に続きます。何も問題が起きていないときでも「何か悪いことが起きるかもしれない」と感じてしまい、結果として日常の中に休まる時間がなくなってしまいます。
向き合い方のヒント
理由が分からない不安に出会ったときに大切なのは、「原因を探しすぎないこと」と「身体のケアを整えること」です。
- まずは深呼吸やストレッチなどで、身体の反応を落ち着ける
- 思考を追いかけるより、五感に意識を向ける
- 「今は不安なだけ。必ず理由があるとは限らない」と言葉にしてみる
- 眠れていない、食べていない、疲れがたまっていないかを確認する
また、不安が何度も繰り返される場合は、医師や心理職に相談することも有効です。「理由が分からない」ことにひとりで耐え続けるよりも、誰かと共有しながら整理していくほうが、不安はほどけていきます。
当てはまることがあった方へ
「どうしてこんなに不安なのか、分からない」。そんな気持ちを抱えているときこそ、自分を責めずに一度立ち止まってみてください。
不安には、思考では説明できない体の反応や、気づかないうちにたまった疲れが影響していることもあります。
無理に理由を探すよりも、まずは「今の自分にできる小さなケア」を続けていくことが、回復の第一歩になることもあります。
一人で抱えきれないと感じたら、迷わず専門家に相談してください。少しずつ、不安と折り合いをつけていく道を一緒に見つけていきましょう。