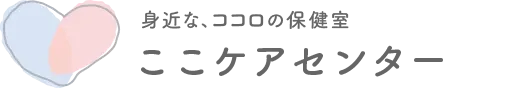長期の休みに入ると気が抜けてしまったり、逆に落ち着かなくなったりすることはありませんか?普段は「休みたい」と思っていたはずなのに、いざまとまった休みに入ると気分が沈んだり、疲れが取れないまま終わってしまったりする。そんな経験に心当たりのある方も多いかもしれません。
実は、長期休暇とうつ症状のあいだには一定の関連があることが、これまでの研究から紐解くことができます。休暇は心身を回復させる貴重な時間である一方で、気分や生活リズムに影響を与えるリスクもあるのです。
休暇がもたらす変化とその影響
人はある程度の「日常のリズム」によって気分を保っています。毎日同じ時間に起きて、通勤して、仕事をして、人と関わる。こうしたルーティンは、意識していないところでも自律神経や睡眠のリズムを整え、心の安定に貢献しています。
ところが、長期休暇に入るとそのリズムが大きく崩れます。遅くまで起きて、昼頃に起きるような生活が続くと、概日リズム(体内時計)が乱れ、朝の光を浴びる機会も減り、セロトニンなど気分を安定させる神経伝達物質の働きも低下しやすくなります。その結果、気分が沈みがちになったり、意欲が出にくくなったりするのです。
さらに、職場や学校などで人との交流が途絶えることも、気分の変化に影響します。社会的なつながりは、抑うつ症状の予防要因としても知られています。予定が減ることで孤立感が高まり、それが気分の低下につながることもあるのです。
休み明けにうつ症状が強くなる理由
うつ病の方にとって、長期休暇明けのタイミングは特に注意が必要です。リズムが崩れたまま急に社会復帰しようとすると、体や心がついていかず、過剰な疲労や無力感を抱きやすくなります。
また、「せっかくの休みなのに何もできなかった」「休んでも気分が晴れない」といった否定的な思考が強まると、自己批判や無価値感につながりやすくなります。このような傾向は、うつ症状を長引かせる一因になることもあります。
長期休暇とどう向き合えばいいか
では、長期休暇をうまく活用するにはどうすればよいのでしょうか。まず大切なのは、「休むことに意味がある」と理解することです。何かをしなければならない、充実させなければならないというプレッシャーは不要です。うつ症状の回復期においては、何もしない時間も治療の一部です。
また、休暇中でもある程度の生活リズムを保つことがすすめられています。たとえば、朝は決まった時間に起きる、毎日短時間でも外に出る、簡単な家事や食事の支度をルーティン化するなど、小さな活動の積み重ねが気分の安定につながります。
活動が減りすぎてしまうと、抑うつ症状が悪化することが知られています。行動活性化という治療的アプローチでも、意図的に小さな行動を増やすことで、気分の回復が促されることが報告されています。
必要なときは専門家に相談してください
もし、休み中や休み明けに気分の落ち込みが続いたり、これまで楽しめていたことに関心が持てなくなったりするようであれば、うつ症状の可能性も考えられます。一時的なものかどうかを見極めるためにも、医師や公認心理師などの専門家に相談してみることをおすすめします。
うまく休めないことに悩む必要はありません。少しずつ、自分に合った休み方を見つけていくことが、長い目で見て心の安定につながっていきます。予定がなくても、何かをしなくても、休むことに価値はあります。まずは自分のペースで、心と体を整えていきましょう。