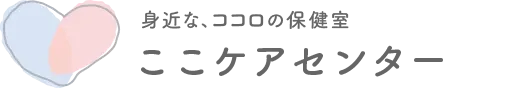人よりも不安を感じやすい、ささいなことをいつまでも気にしてしまう、失敗を恐れてなかなか行動に移せない。こうした傾向は「性格」や「気の持ちよう」と片づけられがちですが、心理学や生理学の研究では、これらの特性には明確な原因があることがわかっています。
その中心にあるのが「神経症傾向(Neuroticism)」と「行動抑制系(Behavioral Inhibition System:BIS)」です。これらは、不安や抑うつの起こりやすさを理解するうえで重要な鍵となります。
神経症傾向とは何か
神経症傾向とは、ストレスや不安、怒り、悲しみなどのネガティブな感情を感じやすく、それが長く続きやすい傾向を指します。心理学的な性格モデルである「ビッグファイブ」でも主要な次元のひとつとして位置づけられています。
神経症傾向が高い人は、同じ出来事でもより強い不安や落ち込みを感じやすい傾向があります。たとえば、他人の小さな表情の変化を「怒っているのでは」と受け取ったり、失敗した出来事を繰り返し思い出してしまったりします。これは、感情の強さだけでなく、感情を調整する力が働きにくいという特徴も含まれます。
この傾向自体が「悪い」わけではありません。危険を察知して慎重に行動する力でもあり、環境によっては非常に適応的に働くこともあります。ただし、ストレスの強い環境や予測の難しい状況では、過剰な不安や自己批判につながり、うつ病や不安障害のリスクを高めることがあります。
行動抑制系(BIS)の働き
行動抑制系(BIS)は、心理学者グレイが提唱した理論で、人が罰や危険、未知の状況に直面したときにどのように反応するかを説明するものです。BISが活発な人は、「失敗したくない」「怒られたくない」といった罰への感受性が高く、危険を避けるために行動を抑える傾向があります。
たとえば、会議で意見を求められたときに「間違えたらどうしよう」と感じて発言を控える、上司に注意されたあとで数日間ずっとそのことを気にしてしまう、といった行動がそれにあたります。これは、脳が不安や危険信号に強く反応し、回避行動を引き起こしている状態です。
この行動抑制系は、不安や恐怖の体験に関与する脳の仕組みと関連しており、BISの働きが強い人は、日常の中でも常に「リスクを探すモード」に入りやすくなります。そのため、他の人なら気にならないような刺激にも敏感に反応し、慢性的な緊張や疲労を感じることがあります。
神経症傾向・BISと不安・うつの関係
神経症傾向とBISは、どちらも不安や抑うつの原因として働くと考えられています。つまり、これらの気質を持っている人は、ストレスや喪失、職場の人間関係の変化といった外的要因に直面したとき、感情的なダメージを受けやすく、回復に時間がかかる傾向があります。
研究でも、神経症傾向の高い人はうつ病や不安症の発症率が有意に高いことが示されています。これは、ストレスを感じた際にネガティブな情報に注意が偏りやすく、悲観的な思考が持続するためと考えられています。BISの過剰な反応も同様に、危険回避行動を強め、結果的に社会的な孤立や自己効力感の低下を引き起こすことがあります。
向き合い方の工夫
神経症傾向やBISの特性を変えることは簡単ではありませんが、その影響を和らげる方法はあります。まず、自分が不安を感じやすいタイプであることを理解することが大切です。「なぜ自分だけこう感じるのか」ではなく、「こう感じやすい傾向がある」と認識することで、必要以上に自分を責めることを防げます。
また、ストレスを感じたときに自動的に起こる思考や反応を整理するトレーニング(認知再構成法)や、感情を受け流すスキル(マインドフルネスなど)も有効です。BISが強い人は「行動を抑える」傾向があるため、小さな成功体験を積み重ねて行動範囲を広げることが、過剰な回避を緩める助けになります。
まとめ
神経症傾向や行動抑制系は、生まれつきの気質として誰にでも程度の差があります。これらの傾向が強いからといって異常というわけではなく、慎重さや共感力として働くことも多くあります。ただし、強いストレス下では不安や抑うつを引き起こす要因となるため、早めの対応が大切です。
必要な時は専門家に相談してください。 医師や公認心理師などの専門家は、心理教育や認知行動療法などを通して、気質と上手に付き合う方法を一緒に考えてくれます。気質そのものを変えようとするよりも、環境と心の使い方を調整していくことが、安定した生活を取り戻す第一歩になるかもしれません。